「夏うつ、熱中症、感染症」暑すぎる夏が引き起こす健康被害<予防と対策>
この投稿を読むとわかること

気候変動による温暖化は年々過酷になる猛暑をもたらしました。2023年の7月は過去最多の猛暑日数を記録。全国で35℃を超える危険な暑さが続出しています(※)。過酷な暑さがもたらす健康被害は甚大で、その影響は熱中症のような直接的なものにとどまりません。暑すぎる夏は私たちの健康にどのような影響及ぼすのでしょうか。そしてそれを予防する方法は?
暑すぎる日本の夏が健康被害の引き金に
2021年に算出された日本国内30年間分の平均気温値である「平年値」は、100年前と比べて2度も高くなっています(※)。気候の変化は猛暑以外にも、大雨や高潮、洪水、土砂災害など、多くの異常気象や自然災害を引き起こしていて(※)、被害が報道されない日はないと言っていいほどです。

暑熱が引き起こす健康被害も、温暖化によって起こる看過できない被害の一つ。日本全国において、気温が高くなることによる超過死亡(予測死亡者数と比較して、増加した分の死亡数)が増えています。国内の全年齢を対象にした研究では、2031〜2050年、2081〜2100年には、熱ストレスによる超過死亡数が2010年を基準にして2倍以上になるという結果が出ました。
猛暑が持病を悪化させることを危惧する声(※)や、気温の上昇が自殺率の増加に関連していることへの指摘もあります(※,223-225)。
気温差がもたらす健康影響にも気をつけなければなりません。極端な気温差が寿命を少なくとも1年短くしているとする研究や、日中の気温差が心筋梗塞や狭心症、心不全に代表される心血管疾患のリスクになっていて、気温が1度上がることで年間約15万人が心血管疾患で超過死亡するという推計が発表されています(※)。
「熱中症、夏うつ、こもり熱」暑さが引き起こす危険な症状
熱中症は命にかかわる危険な病気。高齢者の熱中症の多くは自宅で発症しています(※)。高齢になると暑さや喉の渇きを感じにくくなるため(※)、年々暑さが厳しくなっている今、自宅にエアコンがなかったり、エアコンを使う習慣がなかったりすることは熱中症に直結するリスクとなりかねません。生活様式を見直すことが大切です。

「こもり熱、うつ熱」など、身体から熱を逃すことができず、高体温状態になってしまう症状にも注意が必要。日本の夏の特徴である高温多湿が引き起こす「うつ熱」は発熱と違い、解熱剤が効きません。手足が熱いなど、うつ熱の症状が疑われる場合には水分補給をし、ぬるめの水で身体を冷やして涼しい場所で過ごしましょう(※)。
暑熱のせいで食欲が低下したり、よく眠れない日が続いたりすることで、疲労が溜まり、季節性感情障害「夏季うつ」を引き起こすことも指摘されています。室内と屋外の気温差が自律神経を乱すことも相まって、暑すぎる夏が心身に負担をかけてしまうのです。単なる「夏バテ」とは違い気分の落ち込みなどメンタルへの悪影響が見られることが特徴です(※)。
「マラリア、デング熱、ジカ熱」蚊やダニによる感染症
気温が上がることで、感染症を媒介する蚊の生息域が広がり、活動期間が長期化することがわかっています。2019年9月には京都府や奈良県でデング熱の発症が確認されました。日本に生息していなかった種類の蚊やダニによる感染症のリスクが高まって、こうした感染症例が国内各地で発生することが危惧されています。

マラリアを媒介するハマダラカや、デング熱やジカ熱を媒介するネッタイシマカは現在日本には生息していませんが、他国から侵入があった時に、日本が生息に適した気候になっていれば定着してしまう恐れがあります。幼虫やさなぎが発見されたケースは過去すでに報告されています(※)。
現在日本に生息している蚊についても、デング熱を媒介するヒトスジシマカの生息域の最北は、1948年時点の栃木県から2016年には青森県まで広がりました。この先、温暖化による最も過酷な気温上昇のシナリオをたどることになれば、21世紀末には北海道の一部にまで分布する可能性が高いとされています。(※,230-234)。
お年寄りや子ども、基礎疾患を持つ人、低所得者などへの不平等な影響
65歳以上の高齢者の暑さに関連する死亡率は、過去20年間で1.5倍以上にも高まりました(※)。熱中症の発症、死亡リスクは所得や生活水準と関係するという研究も多く、社会的に立場の弱い人がより大きな危険に晒される可能性があります。子どもや胎児、妊婦は、ことに暑さに弱く下痢症にかかりやすいという報告もありました。

こうした気候変動の不平等な影響は、地球規模でも起こっていて、WHOは2030年から2050年に子どもの低栄養、マラリア、下痢症、暑さが引き起こす高齢者の死亡で、約25万人も死者数が増加すると予測しています。背景には子どもや高齢者、途上国で暮らす人々、スラム地域など都市部の貧困層や沿岸部住民が、より高いリスクを強いられている現状があります(※)。
酷暑に起きる自然災害の脅威
外気温の変化は、水や食品を媒介する感染症やインフルエンザのような感染症の広がり方を変えるため、自然災害時に予期せぬ健康被害が重なりやすく、被害状況を何重にも悪化させます。被災経験や過酷な避難生活によるトラウマ・PTSDのような、自然災害後のメンタルヘルスの問題も重大な健康被害です。

その他にも温暖化と大気汚染の複合的な影響で、心血管疾患や呼吸器疾患による死亡が増加する可能性など、研究中の影響や被害が数多くあります。こうした研究が進められている最中であるため、現段階では緊急性が「とても高い」と評価されていない影響が今後大きな被害を出す可能性、また未知の被害が起こる可能性も十分にあり得ます(※,242-244)。
夏の健康被害にどう対処する?
気候変動が自然災害を増加させることを実感している人は多いと思います。しかし、災害が被害の連鎖を引き起こし、そうした影響が流れ着く終着点の一つに人の健康があることはまだあまり語られていません。
例えば、今年7月には17〜23日の一週間の間に9,190人が熱中症で救急搬送されました(※)。救急出動が急増して体制がひっ迫することで搬送に影響が出てしまいます。自然災害で交通機関が止まれば、持病のある人や病院に行く必要がある人の通院が妨げられることになるでしょう。このように、気候変動の健康への悪影響はじわじわと波紋のように広がります。
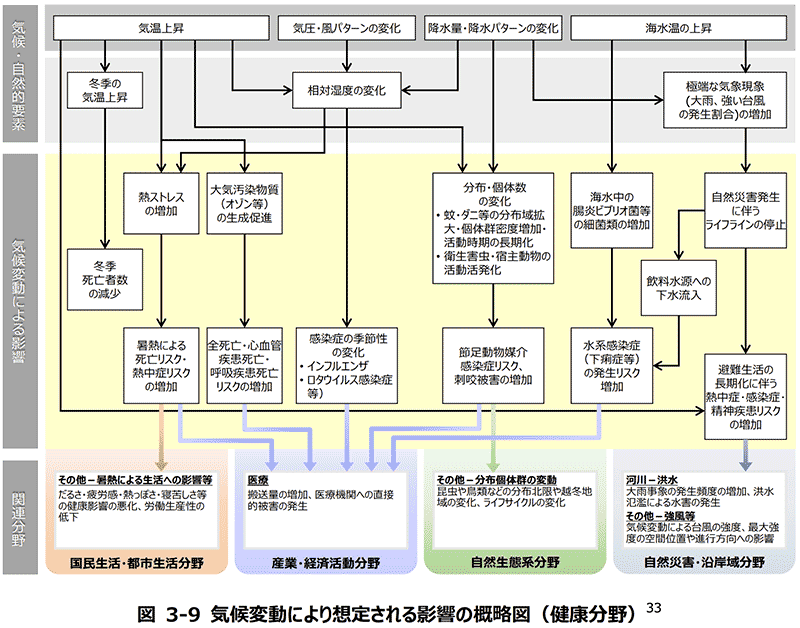
気候変動により想定される影響の概略図(健康分野)
常軌を逸した暑さのように、健康被害を引き起こす異常気象。被害を減らし、これ以上悪化させないためには、気候危機を回避するためのアクションと、健康被害を防止し、軽減させる行動様式の刷新を同時に進める必要があります(※)。
大変なことのように聞こえますが、環境のための行動と、健康増進のための行動は繋がっていることが多いのです。

例えば、肉食を減らして野菜をたくさん食べれば、低炭素と健康的な食生活を同時に実践することができます。車の利用を自転車に変えれば、二酸化炭素排出を抑え、大気汚染を抑制しつつ、運動によって心肺機能の強化を行うことができます。
エアコンの適切な使用も大切。設定温度を調整して、除湿運転を効果的に使用、あまりつけたり消したりしないようにすれば、熱中症対策と節電の両方につながります。(※)。
健康と環境、どちらも大切に暮らすために
地球温暖化による健康被害はもう起きています。どんな未来がやってくるのかを正確に知ることはできず、現在の予測が楽観的すぎる可能性も小さくありません。
けれど、私たちにはどんなシナリオを選ぶのかを決めることができます。産業革命以降からの気温上昇を1.5度未満に抑えることで、気温に関連した死亡の大幅な増加を抑制できることがわかっています。未来は選択と行動で変えられます。
グリーンピースは、科学的な調査に基づいて、仕組みを変える効果的なアプローチを行い、地球の未来と私たちの健康な暮らしを守るための活動を続けています。グリーンピースへの寄付を通して、気候変動を止めるためのアクションに参加してください。